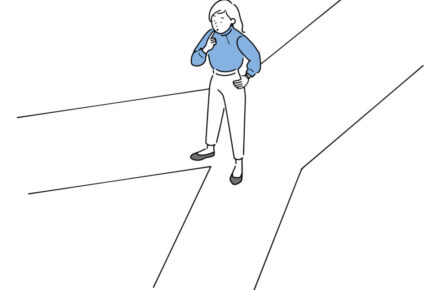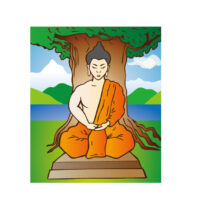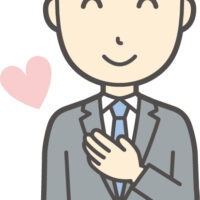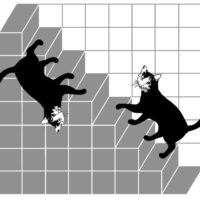塾長の考え(現在の結論)その5
【結論③】
生徒が勝手に「自習」したところで、
成績が上がっていくということはない。
(成績不振の原因は「別」にある)
これが前回のブログの内容だ。
3月に入ってから昨日まで、
新規の親御さんや生徒と面談を、
60人以上してきたが、
そのときに何度も確認できた。
「自習」は危険である。
危険と言うと大げさに聞こえるが、
少し解説してみる。
まず「自習」という言葉に対して、
ほとんどの親御さんが、
いい印象を持っている。
どうやら、
「自習」=「自主学習」
というイメージを持っているようだ。
だが、
この2つは決して同じではない。
そもそも混同していること、
この時点で違う。
自習を「売り」にしている塾、
よって、
毎日塾に通えることを、
「いいことですよ!」
と宣伝する塾があるが、
親御さんたち(生徒も)同様、
彼らも、
決定的な思い違いをしている。
(純粋に生徒のためなら思い違い)
(塾の戦略の場合は別に狙いがある)
自習とは、
学校の先生(指導者)が与えた課題を、
生徒が自分の力で学習すること。
※場所は自宅以外(3つ)
①学校(教室) ②塾 ③予備校
自主学習とは、
特にやることを指定されなくても、
生徒自らが「主体性」をもって、
自分がやりたいことや必要なことを、
学習していくこと。
※場所は自宅(または寮)
自立型個別学習方法を開発し、
自立型個別指導を、
指導方法として実施している、
北斗塾の塾長である私だけが、
この違いに気付いているようだ。
特に、
学習している場所(空間)で、
その学習の中身(性質)が、
「変わる」という点。
ネット上のどこにも、
自習と自主学習との認識の違いが、
意識の違いとなり、
その意識の違いが、
受験勉強の成果の違いになる。
そんなことは、
誰も言って(書いて)いないからだ。
今後はここで活字にした以上、
この内容を前から知っていたと、
吹聴(主張)する塾長や、
わざわざ会場を借りて、
もっともらしく講演する人も、
あちこちから出てくるだろうが、
その人たちは何もわかっていない。
その人たちは研究者の立場ならば、
現場の実践を積んでいないため、
本質が肌感覚でわかっていない。
あるいは、
塾で自習できることを「売り」に、
そのメリットを常日頃から、
親御さんたちに植え付けようと、
宣伝(ブログ含む)をする、
人たちも、
根本的に指導に対しての、
「考え方」が違う。
蛇足にはなるが、
講演する人たち(特に学校内で)
の目的も生徒の学力向上ではない。
「集客」である。
親御さんたちも生徒たちも、
「情報大洪水」の時代の中で、
生きていくうえで今まで以上に、
判断力が問われる時代になった。